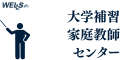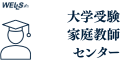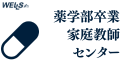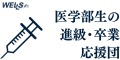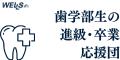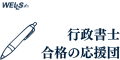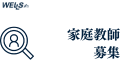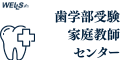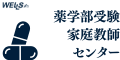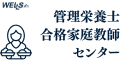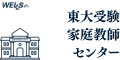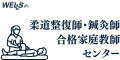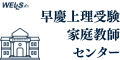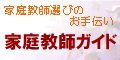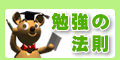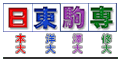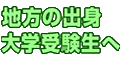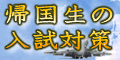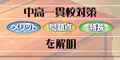まず現状を知る:留年が起きやすい理由
- 情報量が膨大:基礎(物理・化学・生物)から臨床・実習まで横断。復習が遅れると一気に雪だるま。
- 試験のハードルが高い:進級試験・実習評価・卒試・CBT・国試…それぞれ対策が異なる。
- 再試の回数制限:大学によっては再試チャンスが少なく、1科目の取りこぼしが留年に直結。
留年の影響:精神的ダメージ(自己効力感の低下・孤立感)、経済的負担(授業料・生活費の延長)。「早めの可視化」と「計画の実行力」が最大の予防策。
留年を防ぐ5つの原則
- 週単位で逆算(試験日→週→日へブレークダウン)
- 弱点の早期特定(A=維持/B=補強/C=再学習の3分類)
- 毎日“短い復習”(学習直後24時間・1週・1か月の3タイミング)
- 演習主導(講義→要点整理→過去問→類題で定着)
- ヘルプを早く頼む(家庭教師・先輩・友人でボトルネックを即解消)
目標設定とスケジュール管理
- 短期目標(1週間):到達範囲を具体名詞で。「口腔解剖:筋・神経の走行を説明できる」「保存:窩洞形成の手順を口頭で60秒」。
- 長期目標(学期~国試):進級・CBT・卒試・国試のマイルストーンに必要点数と必要単元を割当。
- ツール:Googleカレンダー+タスクアプリ(今日のToDoは3個まで)。実習・課題の〆切は必ず色分け。
科目別アプローチ(難易度に応じて)
- 基礎医学:講義→要点カード化→図で再現→小テスト。反復で“用語⇄意味⇄図”を結ぶ。
- 臨床系:過去問と症例で出題形式に慣れる。手技・プロトコルは手順化して口頭確認。
- 実習:チェックリストで事前リハ(手順・器具・安全)。評価基準を先に把握。
グループ学習の使い方
- 目的と役割を明確に(出題範囲分担→5分講義で相互教え合い)。
- 脱線防止にタイムキーパーと成果物(1枚要点シート)を必ず残す。
自己管理のコツ
- 睡眠・食事・運動の3本柱を固定。
- 1日の終わりにできた3つを記録(自己効力感の回復)。
試験対策の実践
- 定期試験:授業当日24時間以内に“5問だけ”自作小問→週末に解き直し。
- 過去問・模試:3周(1周=理解メモ、2周=タイムトライアル、3周=誤答のみ)。
- CBT:分野別に時間配分を決め、計算・統計・感染制御は毎日1セット。
- 暗記:短時間×高頻度。フラッシュカード/音読要約/60秒口頭説明。
- 失敗時のリカバリー:48時間以内に原因分析→再試までのミニ計画(単元・時間・確認方法)を作成。メンタルが重い日は“15分だけ”ルールで着手。
家庭教師・外部リソースの活用
- ピンポイント補強:理解が進まない単元を短期間でブレイクスルー。
- 計画の伴走:週次レビューと到達度テストでズレを即修正。
- 柔軟スケジュール:実習期は時短集中、直前期は増枠。オンライン併用で移動ゼロ。
- 仲間活用:要点共有・模試後の相互解説で視点を増やす。
すぐ使える1週間テンプレ
- 月:講義復習90分(要点カード化)/過去問10問
- 火:弱点単元60分+口頭60秒説明×5本
- 水:小テスト20分→誤答直し40分
- 木:類題演習60分→解法メモ作成
- 金:実習チェックリスト見直し30分
- 土:模試 or 長時間演習(90–120分)
- 日:週次レビュー30分→翌週計画作成15分
迷ったら、相談を
「どこから直せばいいか」を一緒に可視化します。無料相談・体験のご希望は info@wells-inc.co.jp まで。
留年を“未然に防ぐ計画”で、確実に前へ進みましょう。