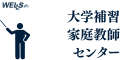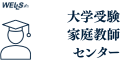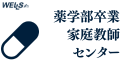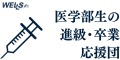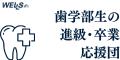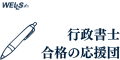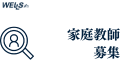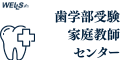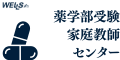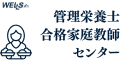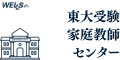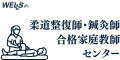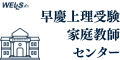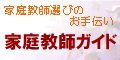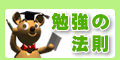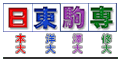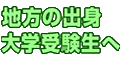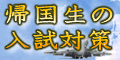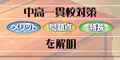大学の専門科目は量・速さ・自走力が勝負。ウェルズは「何からどうやるか」を明確化し、短期で点に変わる学びへ最適化します。
共通:補習の進め方(全科目)
- 講義→要点抽出→演習→口頭チェックの4サイクルで定着
- 重要図表は自分の手で再現(説明できる=使える知識)
- 直近試験に合わせた頻出リスト&誤答パターン潰し
科目別サポート(つまずく理由/指導の要点/得点化のコツ)
解剖学・口腔解剖
- つまずき:範囲過多・用語三言語・経路把握
- 指導:実習前プレビュー+実習後リキャップ/神経・血管は“起点→経路→支配”で線に
- コツ:孔と通過構造、筋起始停止+作用+支配神経をカード化
組織学・口腔組織
- つまずき:像が読めない/まとめに時間がかかる
- 指導:標本画像100本ノック/“どの臓器のどの層か”の位置意識
- コツ:写真問題テンプレ(特徴語→判断ルート)を作成
生理学・口腔生理
- つまずき:前提抜けで連鎖的に不明
- 指導:章頭概念マップ→式・グラフを自作/毎回ミニ口頭試問
- コツ:酸塩基・循環・神経は典型設問の因果説明を練習
生化学・口腔生化学
- つまずき:目に見えない抽象性・経路暗記の重さ
- 指導:代謝経路は目的→出入口→制御点で理解/疾患・薬理と接続
- コツ:試験前は制御酵素と補因子だけを横断復習
薬理学・歯科薬理
- つまずき:分類&機序の渋滞
- 指導:機序→効果→有害事象→禁忌の一枚表/作用機序は図解で
- コツ:鎮痛薬・局所麻酔・抗菌薬は適応と禁忌を即答レベルに
免疫学
- つまずき:用語多・経路類似
- 指導:自然/獲得・液性/細胞性の二軸整理/BCR・TCRの違いの言語化
- コツ:アレルギー分類・MHC I/IIは図で瞬答
病理学・口腔病理
- つまずき:分類迷子・像と言葉が結び付かない
- 指導:臓器別スキーマ/組織像⇄臨床像の往復
- コツ:悪性度・鑑別の決め手フレーズをセット暗記
微生物学・口腔微生物
- つまずき:対象広すぎ/臨床紐づけ不足
- 指導:グラム性・形態→疾患→治療の三段跳び/口腔常在菌は疾患連関で
- コツ:ワクチン種別・伝播様式は表で秒答
衛生・公衆衛生(口腔衛生)
- つまずき:範囲広・改正多
- 指導:最新法改正に準拠/頻出テーマの図表化
- コツ:感染症分類・母子/学校保健は白地図暗記で固定
口腔外科
- つまずき:鑑別の軸が曖昧
- 指導:頻出疾患の鑑別チャート/受傷機転→画像→処置の流れ
- コツ:合併症・禁忌・術前後管理を症例ベースで反復
保存(修復・歯周・歯内)
- つまずき:材料・術式・診断基準の断片化
- 指導:症例→診断→術式→材料選択の臨床導線訓練
- コツ:窩洞分類・材料特性・根管手技はミニテスト連打
補綴(クラウンブリッジ・有床・インプラント)
- つまずき:基礎と臨床の接続不足
- 指導:設計原則→適応→手順→トラブルの一貫練習/症例写真多用
- コツ:動揺度・各分類・術式フローはチェックリスト化
矯正
- つまずき:抽象度高・装置機序が霧
- 指導:Angle・咬合・生体反応を軸に再構築/セファロ読影の型を習得
- コツ:装置の作用方向と固定概念を図で瞬答
小児歯科
- つまずき:発達・歯の異常・全身の横断整理
- 指導:Hellman段階×処置の対応表/有病児対応もケースで
- コツ:乳歯特性・保隙・口腔粘膜疾患は頻出語を画像と対で
進め方(例)
- 現状診断(到達度テスト&ヒアリング)
- 2〜4週間の短期スプリント設計(科目×目標×週次メニュー)
- 毎回:到達チェック→誤答分析→宿題設定(15分で復習完結設計)
- 直前1〜2週:頻出だけ総点検のラストパス
よくあるお悩み、こう解決します
- 「ノートが散らかる」→配布テンプレで“試験に出るノート”へ
- 「用語が頭に入らない」→口頭試問と1分スケッチで定着
- 「時間が足りない」→優先順位マップでやる/やらないを可視化