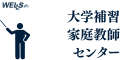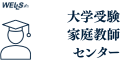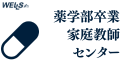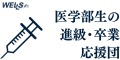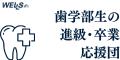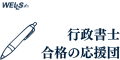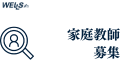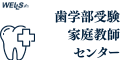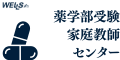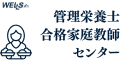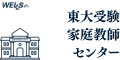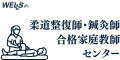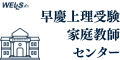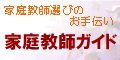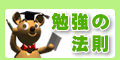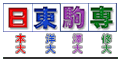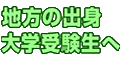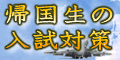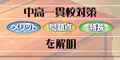共用試験とは
4年生後期に全国一斉で実施される共用試験は、5年からの臨床実習に必要な知識(CBT)・技能と態度(OSCE)を評価する試験です。
不合格=進級不可・実習参加不可。追試であっても確実に突破したい最重要関門です。ここで固めた知識と手技は卒試・国試にも直結します。
まず押さえる全体戦略(逆算プラン)
- T–12〜8週間:基礎系(解剖/生理/生化/病理/免疫)を総点検。画像・機序を“説明できる”レベルへ。
- T–8〜4週間:臨床系(口外/小児/保存/補綴/放射線など)を横断整理。鑑別の決め手・初期対応を暗記。
- T–4〜2週間:CBTは本番同条件のブロック演習(60分×6)→復習は演習時間の2倍。
- T–2週間〜前日:OSCEリハ(動画撮影+自己採点)/口頭試問/頻出画像の総点検。
4年後期の期末と並走するため、週単位のスプリント管理が鍵。
「やること・やらないこと」を最初に決めて、迷いを減らすのが合格最短ルート。
CBT攻略ガイド
出題:60分×6ブロック=計320問(うち採点240/試行80)※採点対象の識別は不可。
学習配分の目安:基礎系60%|臨床系30%|公衆衛生・法規10%
高得点のコツ
- 機序→因果→臨床像で語れるか?(“覚えた”でなく説明できる状態へ)
- 画像対策:放射線画像・組織像・口腔病変写真は毎日1セット。
- 錯問ノート:誤答の“勘違いポイント”を1行で言語化→翌日/3日後/7日後で再確認。
- ブロック模試の運用:本番同条件で解く→復習は出題根拠まで辿る(教科書・講義スライドに必ず帰る)
重点領域の例
- 基礎:解剖(神経・血管走行/孔と通過構造)、生理(調節機構とグラフ)、生化(代謝経路の分岐点)、病理(腫瘍の分類・典型像)、免疫(自然/獲得・MHC・過敏反応)
- 臨床:口外(鑑別と初期対応)、小児(Hellman歯齢・う蝕/外傷)、保存(診断→術式の流れ)、補綴(適応・材料・術式)、放射線(読影の所見語)
目標KPI
- ブロック模試:**70% → 80% → 85%**と段階UP
- 画像同定:30秒以内に主要所見を3点述べる
OSCE攻略ガイド
評価観点(例):安全衛生(手指衛生/感染対策)|コミュニケーション(説明・同意)|手順の正確性|タイムマネジメント
頻出タスクの例
- バイタル測定/基本セットアップ/エックス線防護の説明
- 局所麻酔の準備と確認、印象採得の基本手順、応急処置の判断
- 患者説明:目的→手順→注意点→合意を簡潔に
練習法
- 動画セルフレビュー:チェックリストで自己採点→不足のみ反復
- 鏡前トーク:定型フレーズを10秒で言い切る練習
- ロールプレイ:想定質問に即答できるまで口頭試問
使える定型フレーズ(例)
「これから◯◯の処置を行います。所要時間は約◯分、痛みが出そうな時は手を上げてお知らせください。ご不安な点はありますか?」
よくある失敗 → こう直す
- 過去問だけ:→ 根拠ページに必ず戻る“往復復習”で再現性を上げる
- 基礎を飛ばす:→ 基礎→臨床の橋渡し図(機序→症状→検査→対応)を自作
- 直前一気:→ 毎日45分×2本の固定スロットで“少量高頻度”
- 画像軽視:→ 1日5枚のスライドデッキをルーチン化
- 計画過多:→ 週1回の**“捨てる会議”**で優先度を再調整
ウェルズの伴走(CBT/OSCE特化)
- 初回60分診断:成績・進度・弱点を見える化(優先度マップ作成)
- 専用カリキュラム:基礎→臨床の横断整理、鑑別“決め手”カード、頻出画像デッキ
- CBT本番演習:60分×6ブロック模試→誤答の原因分類→対策を翌週へ反映
- OSCEリハ:動画撮影→ルーブリックで採点→改善ドリル
- 直前2週間の総点検:頻出100テーマの“口頭10秒チェック”/ラストパス
無料相談・体験のご案内
「どこから手をつければいい?」に、あなた専用の逆算プランで答えます。
この一回を、確実な一歩に。共用試験を“合格の通過点”に変えましょう。