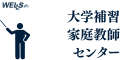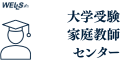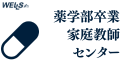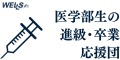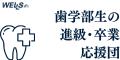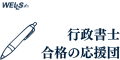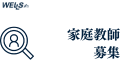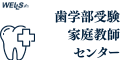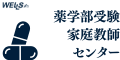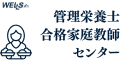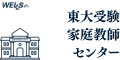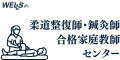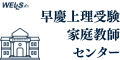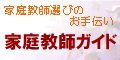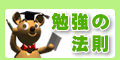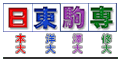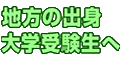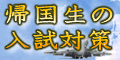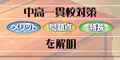新しい知識と技術を次々に吸収していく歯学部の6年間。全体の流れを押さえておくと、自分の現在地と次に来る山場が見え、各科目を“点”ではなく“流れ”として理解できます。
6年間の全体像(早見表)
- 1年生|一般教養・歯学入門 … 余裕のある年。基礎力の底上げが鍵。
- 2年生|解剖・生理・病理ほか基礎系 … 専門の土台づくり。必修の単位死守。
- 3年生|口腔系の基礎・臨床入門 … 臨床への橋渡し。つまずきやすい学年。
- 4年生|臨床歯学本格化 … **共用試験(CBT/OSCE)**を突破して臨床へ。
- 5年生|臨床実習 … 参加型実習で患者対応と手技を習得。
- 6年生|高度臨床・卒試・国試 … 総仕上げ。卒試合格=国試受験資格。
1年生|一般教養・歯学入門
- 外国語・人文・社会・自然科学などの一般教養+歯学入門、早期臨床体験。
- 余裕のある一年なので、生物・物理が不安な人はこの時期に徹底補強。
ポイント
- 評価は筆記だけでなく、レポート・小論文・口頭試問など多様。
- 高校→大学の学び方ギャップ(論述・口述・情報整理)を早めに埋める。
2年生|基礎系の本格化
- 解剖・組織・生理・生化・病理・発生・微生物/細菌・免疫・薬理など。
- 実技実習を通じて人体の構造と機能を多角的に理解。
- すべて必修中心。計画的に進め、落とさない仕組み作りを。
3年生|口腔系の基礎+臨床入門
- 口腔解剖/生理/細菌、歯科薬理、歯科理工など歯学独自の基礎が増加。
- 歯科保存・口腔治療など臨床科目が始まり、内科・外科など関連医学も学ぶ。
- 基礎と臨床の**“つなぎ”**が勝負。断片暗記から因果理解へ。
4年生|臨床歯学の本格化+共用試験
- 有床補綴、歯周、口外、矯正、麻酔、小児などを体系的に。
- 学年末に共用試験(CBT=知識、OSCE=技能・態度)。
- 合格者のみ5年の臨床実習へ進級。ここが大きな関門。
共用試験メモ
- CBT:基礎〜臨床を横断する知識運用力。
- OSCE:手技・態度・コミュニケーションなど臨床能力を客観評価。
5年生|臨床実習(参加型)
- 見学中心から参加型実習へ。各科をローテーション。
- 治療計画立案・診療補助・技工操作など、実務に近い経験を積む。
- 少人数教育で実践力と対応力を磨く。
6年生|高度臨床・卒試・国家試験
- 参加度の高い臨床実習で総合力を仕上げる。
- 卒業試験に合格した者のみ国試の受験資格を得るため、卒試対策が最重要。
- 国試は基礎⇄臨床の統合力と症例対応力がカギ。
学年横断の学び方ヒント
- 基礎⇄臨床を常にリンク:病態生理→診断・処置へ因果で結ぶ。
- 週次リズム:講義直後の“当日復習”+週末の“横断復習”。
- 評価対策の型化:レポート構成、口頭試問の想定問答、OSCE手順書の整備。
- 関門逆算:共用試験・卒試・国試から必要到達度を逆算して配分。
- 記録と見直し:弱点ログ→ミニテスト→再学習のループを回す。
歯学部の6年間は、基礎→統合→実践→総仕上げの連続です。全体像を掴み、山場を逆算して動けば、学びはぐっと進めやすくなります。